

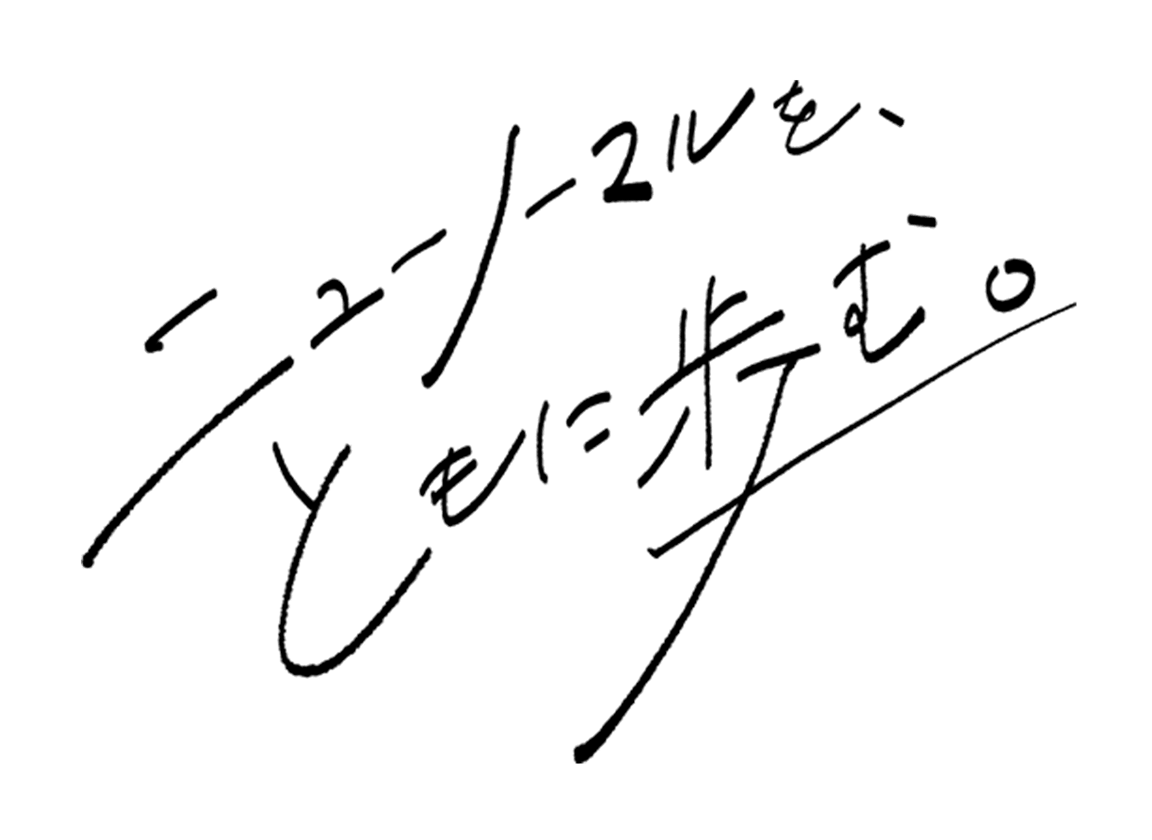



これまでのあたりまえは、
あたりまえではなくなりました。
今、変えられることをひとつずつ、
変えていこう。
人の「想い」は、
新しい常識をつくりだしていく。
誰もが安心して暮らせる社会をつくりたい。
次世代に新たな可能性をつなぎたい。
過去にとらわれず、
人の気持ちを真ん中に
日立システムズは、お客さまとともに、
ニューノーマルの時代を歩んでいきます。



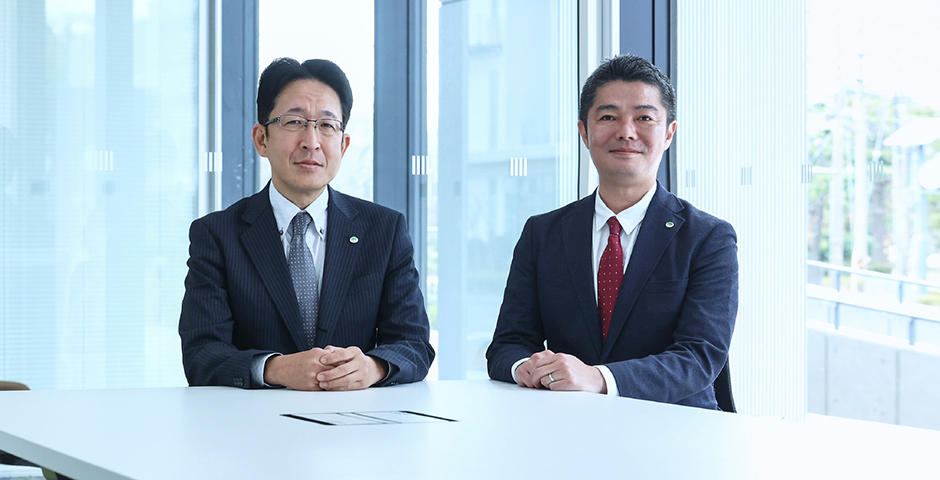
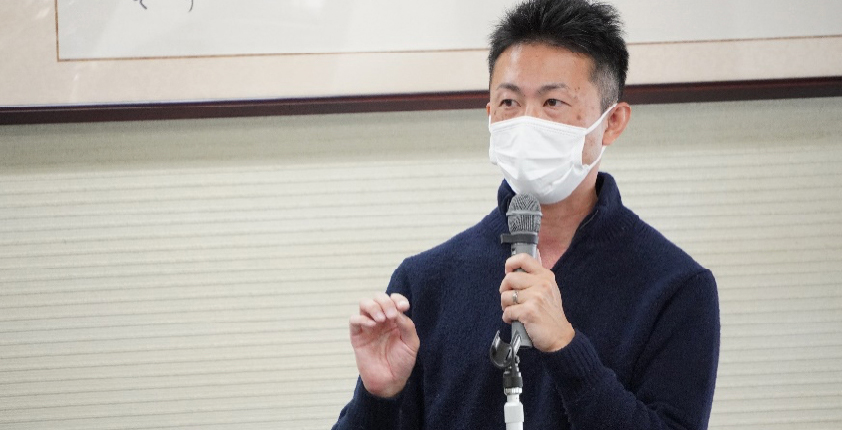






日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。