

2022年5月

こんにちは。田中慎太郎と言います。都内の私立大学の政治経済学部に通う2年生です。ゼミのOGである美咲いずみさんのベンチャー企業でインターンをさせてもらうことになりました。今日は社内システムのクラウド化を検討している会社に伺います。

美咲いずみ
株式会社DXファームCEO
5年間のITエンジニアの経験をもとにフリーのITコンサルとして独立
7年ITコンサルタントを務めたのち、起業

田中慎太郎
大学2年生
DXファームのインターン生
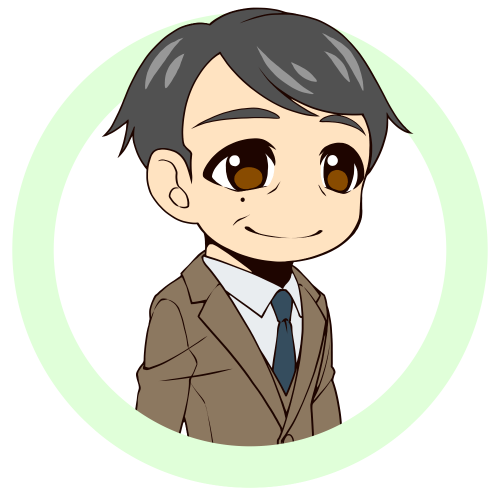
三笠磯雄
ハダリー製紙株式会社 CIO

いずみ
おはようございます。

慎太郎
おはようございます。コンサルというものだから、今日は直接会社に伺うのかと思ったらオンラインミーティングなんですね。

いずみ
はい。オンラインミーティングを始める前に打ち合わせを行う会社についておさらいしておきましょう。

慎太郎
分かりました。

いずみ
ハダリー製紙株式会社について慎太郎くんはどう理解していますか?

慎太郎
名前の通り製紙メーカーで、年商30億円ほどの中堅企業と認識しています。

いずみ
はい、そうですね。ハダリー製紙株式会社は既に30年目を迎える製紙メーカーです。主にトイレットペーパーやティッシュといった家庭紙を取り扱っています。

慎太郎
今回、DXファームに相談したい内容はどのあたりになるんでしょうか?

いずみ
まずお話を聞いてみることにしましょう。そろそろ時間ですね。オンラインミーティングの準備をしましょう。
(数分後)
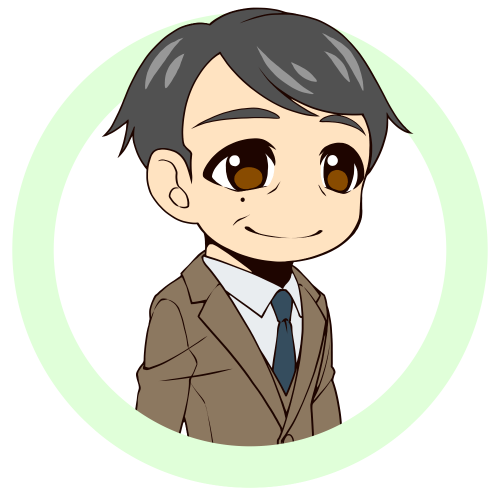
三笠
こんにちは。ハダリー製紙株式会社のCIO、三笠磯雄と申します。

いずみ
はじめまして、DXファームの美咲いずみです。今回、田中も同席します。

慎太郎
こんにちは、田中慎太郎です。よろしくお願いいたします。
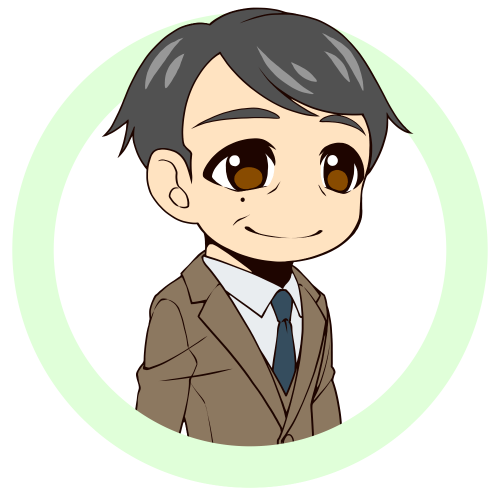
三笠
よろしくお願いいたします。

いずみ
弊社がいつもお世話になっているYMC電子工業の山田さんからの紹介で、今回こうしてアポイントメントを取っていただきありがとうございます。

三笠
はい、山田さんとは大学の同期で、今でも飲み仲間なんです。昨今DXがメディアを賑わしているじゃないですか。ちょうどその話題になったときに、彼のところがスムーズにDX化を進めていると知りました。聞けば、優秀なコンサルがいると。そこでぜひ紹介してほしいとなりました。

いずみ
恐縮です。

三笠
私もDX化を進めなければと思うんですが、いかんせん、どこから始めていいのか分からなくて。お力を借りたく思います。

いずみ
承知いたしました。では、一度こちらの方で現状を把握したいと思います。三笠さんの感じている範囲で結構ですので、御社の今の状況を教えてください。
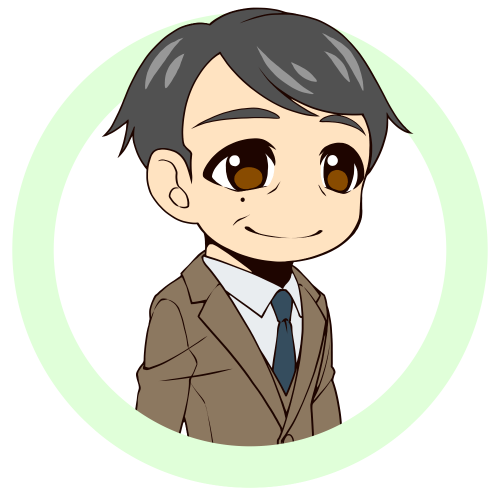
三笠
はい。弊社は、製紙とパルプを扱う小さなメーカーです。今日ご相談したいのは、社内システムがいまだに弊社施設の構内に設置されて運用されているのです。そこで、そろそろDX化をしていきたいと思うのですが、まずはクラウド化ではないかと。

いずみ
なるほど、いわゆる「自社運用」をしていて、DXの第一歩としてクラウド化を検討しているのですね。

三笠
ええ、そういうことです。実際、社員からもクラウド化の要望は高まっているんですよ。

いずみ
コロナ禍でテレワークが一般的になってきましたからね。
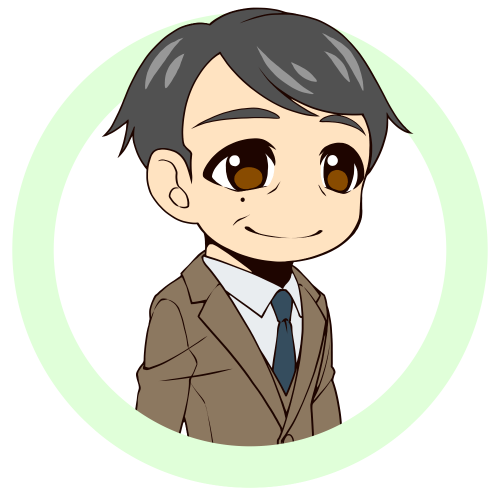
三笠
これまではクラウド化の必要性を感じてなかったんです。社員からも大きな不満もなくて。でも、流石にこのコロナ状況下でクラウド化ができていないと不便なことも多くて。

いずみ
コロナ前でしたら、自社施設内にサーバーや通信回線などの環境を整えてシステム構築や運用を行っていても、そんなに不便な面はなかったですものね。

三笠
ええ、現在のニーズに応えるためにもクラウド化が急務と言えそうです。ただ、弊社にはクラウド化に精通した人間が社内におらず、クラウドに向けて何から始めたら良いのか手探り状態なんです。それに本来の業務がありますからなかなか導入の話が進まなくて、後回しになってしまうんですよ。

いずみ
初めての試みをこれまでのお仕事と同時並行でやっていくのは大変ですよね。

三笠
はい。なにしろ私自身がそこまでクラウドに詳しくないので、まず美咲さんにいろいろと教えていただけると助かります。

いずみ
承知いたしました。では、まず基本的なことから確認していきましょう。
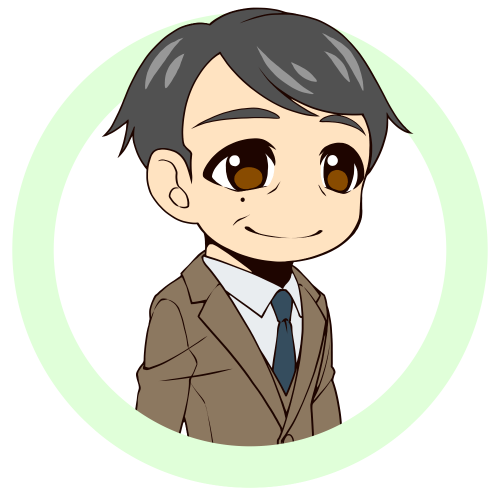
三笠
はい、よろしくお願いいたします。

いずみ
今、御社の置かれている状況はオンプレミス環境というものです。

慎太郎
(オンプレミス?)

三笠
若い社員がそう呼んでいるのを聞いたことがあります。「オンプレミス」ってソフトウェアが施設内に設置されているっていう理解で合っていますか?

いずみ
ええ、プレミス(premise)って元々英語なんですけれど

慎太郎
TOEICの勉強をしているときに単語帳に載っていました。「前提」とか、「構内」って意味ですよね。例文に“on the premise”とありました。「構内で」と日本語訳があったように記憶しています。

三笠
「オンプレミス」ってそういう意味なんですね。

いずみ
はい、本来の意味がそうなりますね。IT業界だと、「オンプレミス」はサーバーやソフトウェアを施設内に設置して運用することを指します。今でこそ当たり前のクラウドですが、一般的になるのは2010年代に入ってからです。実際、「オンプレミス」という言い方は、新しいクラウド運用と区別するために使われるようになったんですよ。

三笠
「オンプレミス」での運用はこれまでずっとあったけれど、「オンプレミス」って言葉自体はつい最近のものなのですね。

いずみ
DXの文脈でよく出てくるようになりましたね。

三笠
そうおっしゃるからには、オンプレミス環境の企業は多いんですか?

いずみ
まだオンプレミス環境でサーバーなどを管理している企業は結構あります。既存システムと統合するのが大変ですし、先ほど三笠さんが仰っていたように、社内にクラウドに精通している人がいなくてなかなかクラウド化を進められないというパターンが多いようです。例えば、次の図をご覧ください。

三笠
身に覚えのあることがたくさん書いてあります。

いずみ
こちらは中小企業庁の「中小企業の身の丈に応じたクラウドサービスの普及支援の在り方について」と題された討議用資料になります。

三笠
まさにうちのような企業のことですね。

いずみ
やはり中小企業庁がこういった資料を作成するように導入がそこまで進んでいない現実があります。

三笠
事業規模が小さくなればなるほど、また経営者の年齢が高ければ高いほど導入が難しくなるようですね。地域間格差も凄そうですね。ベンダーの多くが東京にあるわけですから。

いずみ
この資料が示すように、中小企業のクラウド、ひいてはIT導入の課題には「費用対効果」と「リテラシー」の二つの壁を乗り越える必要があります。

三笠
まさに今私どもが直面している問題です。

いずみ
まず、「費用対効果の問題」という点では、導入効果がわからないこと、コスト負担の不安があること、そして従業員のスキル不足などが考えられます。
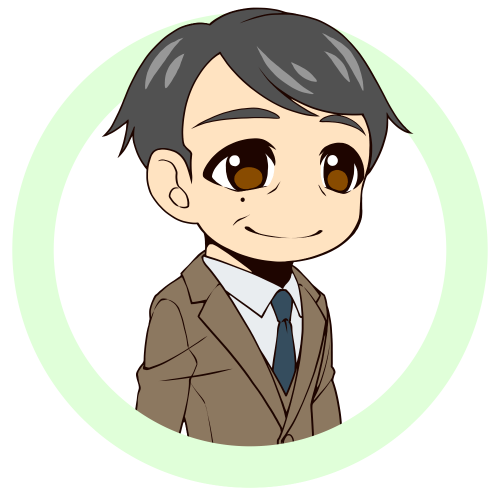
三笠
ええ、実感あります。

いずみ
続いて、「リテラシーの問題」ですが、これはそもそもクラウド導入のイメージができなかったり、ノウハウが不足していたり、クラウドそのものの理解が不足していることですね。

三笠
まさに今の私です。そもそもクラウド化とは何なのか実に理解が曖昧かもしれません。例えば、私は個人的にクラウドのサービスを、MicrosoftのOneDriveとかAppleのiCloudとか使っていますけど、そういったイメージしかありません。

いずみ
そのイメージで全く問題ないです。コンピューターの機能や処理、ソフトウェア、データなどを、通信ネットワークを通じてサービスとして呼び出して、遠隔から利用することを総じてクラウド・コンピューティングといいます。クラウド(cloud)は、「雲」っていう意味で、IT業界だと、ネットワークの先にある外部のコンピューターやシステムを雲のマークで書き表す慣例がありました。

三笠
必要なものは雲から引っ張ってくればいいんですね。

いずみ
はい、その通りです。

三笠
そう考えると、やはりオンプレミス環境は、コロナ禍と相性が悪いですね。テレワークをもっと推進するためにもクラウド化をしていかなければ。

いずみ
オンプレミス環境ではテレワークにも限界がありますからね。実際にクラウドサービスの利用状況を見ると平成30年から令和2年の間に増えています。

三笠
平成30年には6割弱だったのが、令和2年には7割弱に増加しているんですね。一部の事業所や部門での導入よりも全社での利用の方が伸びているのを見るに、やはり便利なのがよく分かります。

いずみ
続いてこちらをご覧ください。
こちらはクラウドサービスの利用内訳です。

三笠
利用しているクラウドサービスは「ファイル保管・データ共有」が最も多いようです。次いで「電子メール」「社内情報共有・ポータル」という風になっていますね。

いずみ
下に行けば行くほどクラウドを高度に利用していると考えてください。

三笠
「営業支援」や「プロジェクト管理」ができると助かるな。

三笠
実際のところ、クラウドを導入するとどうなるのか教えてください。

いずみ
承知いたしました。資料を切り替えますね。
こちらの表をご覧ください。縦軸がクラウド利用の段階を示し、横軸がICTの導入と利用のステップを示しています。

三笠
これはクラウドの導入プロセスですね。

いずみ
ええ、クラウド導入をどうステップしていくのか見ていきましょう。 最初の段階は、社内業務の効率化です。効率化を進めることで、仕事への積極的な参加やスキルアップを促進し、業務の省力化を実現していきます。

三笠
クラウド化で業務効率をあげられるのは助かります。

いずみ
ここからICTの導入を推進していくと、第二段階、社内の見える化を実現できます。業務プロセスが効率化され、既存製品・サービスが高付加価値化されます。

三笠
コロナ禍でテレワークをするようになって各々が何をしているのか把握しにくくなりました。その辺りも、クラウド化で分かりやすくなるということですね。

いずみ
はい、その通りです。見える化による継続的な高付加価値化が進むと、ビジネスモデルを変革する段階になります。ここでは新規製品・サービスの展開をしていきます。

三笠
クラウド利用で、効率化、見える化、新たなデジタル技術を活用するようになるとビジネスモデルを変革することになりますね。

いずみ
デジタル技術を導入するだけではなく、その結果ビジネスモデルを変革することこそDXの正しいあり方です。トランスフォーメーションしていきましょう。

三笠
何だか非常にワクワクしてきました。クラウド化を進めていきたいと思います。クラウド化を進めるには、どこかそういったサービスを行っているツールベンダーさんにお願いすると思います。サービス選びやベンダー選びで大切なことはありますか?

いずみ
一番大事なことは目的ではなく手段としてクラウド化を成功させることです。単に委託先のツールベンダーを探すのではなく、「ビジネスパートナー」として課題解決を支援してくれるところにお願いしたいですね。

三笠
なるほど、早速資料を取り寄せて検討してみます。今日はありがとうございました。

いずみ
ありがとうございました。

慎太郎
ありがとうございました。

いずみ
いかがでしたか?こうしてコンサルの場に同席してみて。

慎太郎
たくさんの学びがありました。まず、コロナ禍でますますクラウド化が必要になっている現状を理解できました。
また、クラウド化には「費用対効果」と「リテラシー」の二つの壁を乗り越える必要があります。
そして、クラウドを導入することでビジネスそれ自体を変革させられる、DXの実現が可能です。

慎太郎
ちなみに、クラウドを導入しやすいサービスにはどんなものがあるのですか?

いずみ
日立システムズの「おてがるCloudスターターパック」というサービスがあります。

慎太郎
おてがるCloudスターターパック?名前を聞くと簡単に導入出来そうな雰囲気がありますね。

いずみ
名前の通り、クラウド化を支援するサービスになります。

慎太郎
おてがるとは、どのあたりがおてがるなんでしょうか?

いずみ
まず、クラウドサービスの立ち上げに必要な全てをワンストップ提供するところです。クラウドの設計・構築、運用・監視、セキュリティ、ネットワークがパッケージングされています。また、クラウド事業の展開だけでなく、社内のクラウド活用にも利用できる機能がパッケージングされています

慎太郎
ワンストップでやってもらえるなら導入する際の負担が少ないですね。

いずみ
本来、ベンダー間の調整は非常に手間のかかる作業なのですが、クラウド基盤をまるごとおまかせできますので、そういった面倒な作業がなくなります。

慎太郎
その分、本来の仕事に注力できそうです。

いずみ
サポート体制がしっかりしているのは重要です。「おてがるCloudスターターパック」は、24時間365日の有人監視でサービスの安定稼働を実現します。障害発生時には早急な一次対応を日立システムズが行います。

慎太郎
障害発生時にいちいち現場に呼び出されなくていいのなら普段の業務がずっと楽になりそうです。

いずみ
また、ビジネス面のノウハウも提供し、スムーズな事業立ち上げを支援してくれます。日立システムズはパッケージソフトウェアのクラウド版リリースを数多く成功しているので、これまでに培った豊富なノウハウを生かし、サービスの策定や運用体制の構築など、ビジネス面の支援も行ってくれるでしょう。

慎太郎
セキュリティ面はどれくらい安全なのでしょうか?

いずみ
冗長化・暗号化・遠隔地保管で重要なビジネスデータを保護されています。だいぶ専門的な話になりますが、ストレージは暗号化に加えて三重の冗長化を行っています。バックアップはAzureの東日本・西日本リージョン間で複製し、ランサムウェア対策などを含めたデータセキュリティも提供されています。

慎太郎
聞いていると安心できます。ただ、予算などもあり、導入コストが心配な会社も多いのではないでしょうか。

いずみ
その点では、従量課金ではなく、月額定額制なので事業の採算性を確保しやすいと思います。不確定要素の多い、新規事業立ち上げ時のコストをうまくコントロールすることが可能なんですよ。

慎太郎
なるほど、これは素敵なサービスですね。ツールベンダーではなく、ビジネスパートナーとして課題解決を支援してくれそうです。三笠さんにも紹介しましょう。
[野付敦 記]