

あすながN温泉にやってきて、3日が経った。
「ありがとうございます。私が一人で考えるより、ずっと魅力的なプランになりました」
結局、旅館の仕事をほとんど従業員に任せてディスカッションに参加していた沼田は、顔こそ疲れ果てていたが充実感に満ちた表情をしていた。
「こちらこそ、お世話になりました…社に持ち帰って、社長とプランの練り直しをしたものを、また来週お見せしますね」
あすなとナミは挨拶をし、帰路についた。
その頃、ビジネス・キューピッドの会議室では安田と日比野がディスカッションをしていた。
「今朝ほど、ナミからメールで送られてきたクラウドファンディングの案がこれだ」
「…若年層狙いか。クラウドファンディングを使う以上そうなることは想像できていたがな」
あすなたちがまとめたリノベーションプランのポイントは以下のとおりであった。
<いざよい荘の再生プラン>
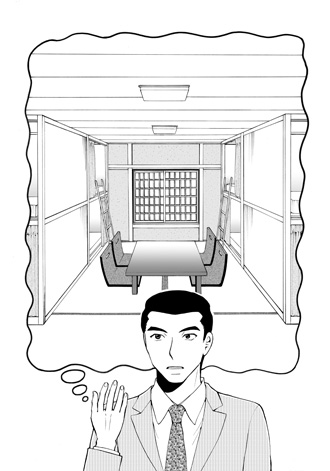
「どう思う?日比野」
安田は資料を見ながら、日比野の考えを聞いた。
「ドミトリールームの設置はいい案だな。1人旅を好む若者には古いタイプの旅館の部屋はむしろ広すぎるかもしれんし、4人ぐらいのグループでドミトリールームを借り切ることもできそうだ。それに、海外からの観光客は相部屋でのコミュニケーションを好む人が多いんじゃないかな」
実はこれこそが、あすなが客室に入った瞬間に思った「違和感」の正体だった。1人暮らしに慣れ切っている若者にとって、広い部屋にぽつねんと座るのは意外と居心地が悪い。
「食堂とバーベキュー場はいささか古典的な発想に見えるが、どう思う?」
「ドミトリールームに作り替える以上、部屋にお膳を並べるスタイルはもう無理があるだろう。仲居などの人件費を抑えることもできるし、個人的には必要な投資だと思う」
「しかし、費用はどれくらいかかるだろうか…?」
「建屋の改装だけでなく、駐車場をつぶしてバーベキュー場のための造成もしなきゃいけないから…億単位の費用になる可能性はある。クラウドファンディングで集められるのはせいぜい数百万円だから、金融機関からの融資が結局はメインになる」
「そうするとクラウドファンディングを、資金集めの手段というよりも、この旅館の知名度を上げるプロモーションとして用いるわけか…」
安田の言うとおり、最近ではクラウドファンディングを広告宣伝やプロモーションの一環として取り入れるプロジェクトが多い。資金集めの大半にめどがついた状態でのプロジェクトは、支援者からのお金の集まりも良くなる傾向がある。
「しかし、いざよい荘の今の経営状況で融資が通ると思うか?」
安田の懸念は、唯一そこにあった。しかし日比野は顔色1つ変えない。
「無理だろうな…このままの案では」
「おいおい、どうするんだよ…」
安田は一瞬たじろいだが、日比野の表情を見て「ふっ」と笑った。
「腹案が、あるんだな?」
日比野は、にやりと笑っている。
「当たり前だ」
あすなとナミが帰って来たのは、その日の昼過ぎだった。
「ただいまー!…あっ、本部長!!」
のんきな声をあげたあすなは、部屋に安田が座っているのを見て、慌てて姿勢を正した。
「はっはっは、のびのび仕事ができていいな、道草」
「…す、すみません」
ナミが手際よくお茶を用意すると、4人でのディスカッションが始まった。「なんで安田本部長がいるのよ…」そんな疑問を、あすなはいったん、胸の奥にしまった。
「結論から言おう。沼田さんとお前たちが持ってきたリノベーションプランを2点ほど修正した。これがその骨子だ」
日比野はスライドを投影した。
<いざよい荘の再生プラン>

数秒間、画面を見つめていたあすなの顔色が、少し変わった。
「え…バーベキュー会場はやらないんですか?なんで?」
「…クラウドファンディングですべてのお金を集めることはそもそも難しい。となると銀行から融資を受けることになるが、それも現状の経営状態では無理だ」
「…だから、土地を売ってそのお金に充てよう、ということですか?」
「そのとおり。これでいざよい荘を立て直す」
「……」
日比野の無表情な話を、隣で安田は静かに聞いていた。その顔には少し、笑みがあったように見えた。しかし、あすなには合点のいかないことがまだあった。
「バスは?」
「車というのは置いておくだけでお金が出ていくんだ。ないに越したことはない。ましてや借金までして買うものじゃない」
「そんな……」
あすながうなだれていくのを、日比野はじっと見ていた。
「不満があるなら、言ってみたら?」
あすなに発言を促したのは、ナミだった。
「…だってこれじゃ、ただ土地を売って建物を新しくするだけじゃないですか…私たちが提案するプロジェクトが、こんなに平凡でいいんですか?」
あすなの射るような視線が日比野に突き刺さる。そして当の日比野はそれでも表情を変えることがない。
その光景を見て、安田がこらえきれないように笑った。
「あっはっは、道草…言うようになったなぁ。平凡でいいんですか?か」
日比野がその発言を聞いて、初めて表情を緩める。
「お前んとこの人材育成のせいだろう?」
「いやいや、お前の過剰な自信が彼女に伝染しただけさ…まぁいい、道草、次は俺が話す番だ」
そう言うと、安田はスライドのページを切り替えた。
上司の話、と言われて、あすなは反射的に座りなおし、姿勢を正した。
<N温泉街の再生プラン>
安田は一つ一つの項目を読み上げ、
「…今のお前なら、意味が分かるだろう?」
と言った。あすなは、こくりと頷いた。
いざよい荘が保有する駐車場をファンドが買い取ることで、いざよい荘に資金を供給しつつ、N温泉全体の観光客の増加を狙っている。バスにしてもそうだ。一つ一つの旅館がマイクロバスを持って駅前の狭いロータリーに押し掛けるより、路線バスを置いてあげた方が効率的だ。
驚きの表情を隠そうともしないあすな。安田は日比野に話しかける。
「結果として、いざよい荘はクラウドファンディングと土地売却だけで資金を工面できるようになる。クラウドファンディングのアピールがうまくいくかが、成功のカギを握るわけだが…」
「それも手を打ってある…つい最近、強力なインフルエンサーに出会ったからな」
日比野の言葉に反応したのは、ナミだった。
「氷室さんね。彼女があのプロジェクトを広報してくれたら、確かに興味を持つ人は増えそう」
とんとん拍子でいろいろなことが決まっていく…そんなプロのやり取りを見て、あすなはただただ、驚いていた。

「ねぇ、ナミさん」
あすなとナミはそろって会社を出た。
「…なんとなく分かってたの?こういう展開になるって」
ナミは笑ってこう切り返す。
「なんでそう思うの?」
「クラウドファンディングで億単位のお金が集まるわけない…それくらいのことなら、ナミさん、最初から気づいてただろうし」
ナミはいろいろなことを気づいていたうえで、あすなを泳がせた、もとい、あすなの自由な発想にあえて異議を唱えなかったのだった。
「ふふふ…そうね。でも良かったじゃない?結果的に、あすなちゃんのアイデアはほとんど採用されたのよ。大変だったけど、よく頑張ったわね」
「そうかなぁ…」
あすなは照れながら、空を見あげた。
夕焼けの赤い空は、N温泉で見たあの景色にも、つながっているのかな。